UGEEN NASyncの広告に触発を受けてシリーズの第何段か忘れましたが、続編です。
クラウドストレージはそのランニングコストから、家庭のコストとしては敵対視されがちです。しかし、それと同等のもの(NAS)を自宅に置くことになった場合も、かなりコストが発生します。ここでいうコストとは、NASを導入するコスト、手間、意識、設定、トラブルシュート、それを支える知識吸収などにまつわる作業時間的なコストも含めています。
ちなみに私はNAS歴10年以上・Windowsサーバー歴15年、インフラエンジニア20年という肩書で、NASの機能も毎日活用していますが、それでいても、手放しに万人にお勧めできるデバイスではないと感じています。
NASのメリットデメリットをしっかり知ったうえで、皆さんにとって最適な選択ができることを願い、本記事を起こしました。
NASの魅力:広がる世界、自分で作る楽しさ
NASは多機能ゆえに、今はただのデータ置き場ではなくなりました。詳しくは以下の記事でも取り上げています。

機能が非常に多く、「使えこなせなさそう」とか、「途中で分からなくなったらどうしよう」とか不安に思うこともあると思います。
しかし、多機能だからといっていきなりすべての機能を使う必要はありません。逆にそのすべての機能を使い切っているユーザーはいるんだろうか。私も使ってない機能がいくつもあります。
初心者は一つの機能だけでも使えればいいと思います。まずは一つの機能に絞って、それを使いこなす。そしてそれを当たり前の毎日にする。その中で、「あ、こういう問題、NASのあの機能で解決できそう」という日が来た時に、改めてNASの機能に触れてみる。そうやって徐々に使っていくことで、なんとなく「自分がこれ出来るようになった」という達成感も味わえます。例えばIPカメラの録画の設定をやってみるとか。
私もNASを導入してからというものの、少しずつ機能を開放していきました。もちろんトラブルや設定に手間取ったこともありましたが、そのたびにレベルアップして、今はネットワークとNASについては怖いものなしになりました。
目に見える安心感:NASがそこにある意味
クラウドはなんだか情報が抜かれてそう、アクセス許可した覚えがあるけど、どのファイルを誰に共有したのか、それが単体なのか、複数なのかというところでなんとなく見えてないことからくる不安があります。その点NASは手元にあるおかげで、なんとなく安心という感覚があることも事実です。本当は、その限りではないのですが、物理的所有による安心感は否定できません。
また、クラウドでは誰でも使えることを目的として、自由度が相対的に下がっています。それについてもNASは自分自身で所有する関係上、自由度が高い設定が可能です。再起動や、設定の変更なども、すべて自分の目の前にある機械における事象だと思うと、クラウドと比べて自分でコントロールできる範囲が広いです。いざというときはバルス初期化という手段も取れてしまいます。
知っておくべき現実:管理コストと必要な知識

NASは機械ですので、当然トラブルも起こったりします。また、トラブルの種は未然に察知して、対策をする必要も出てきます。いくらRAIDである程度守られているとはいえ、それも完ぺきではありません。RAIDの過信も大変危険です。

そしてそのRAIDを過信しないためにも、バックアップはほぼ必須といえるでしょう。NASに外付けHDDを接続して、NAS本体とは別にデータの置き場を確保しておくことが望ましいです。私は当初RAIDを過信してバックアップなしで運用していたところ、大量消失で泣きを見ました…これを読んでいる方々は、私の二の舞にならないでいただければと切に願います。

ただ、幸いなことに、多くのNASでRAIDの健康状態チェックや、バックアップの自動化、そしてバックアップデータの健康状態までも確認するアプリが取り揃っています。(少なくとも私が所有するSynology DS423+ではそれができる)健康状態のチェックを例えば月一回などでスケジュールして、問題があればスマホにメールを送るなどが可能です。
ほかにも、家族でNASを使う場合は、データ(フォルダ)を見せる見せないなどの権限設定もついて回ります。またネットワーク周りで問題があったときにも、アクセスできなくなることもあります。このあたりをきちんとこなしておくことで無用な家族会議も減らすことができるので、管理上必須項目といえるかもしれません(笑)
ここまでの話であればだいぶNAS寄りになりました。管理は確かに手間ですが、そこまで多くの知識を必要としませんので、大体の人が習得可能だと思います。
以下はNASの現実についてです。
多機能性の罠:活用しないと赤字
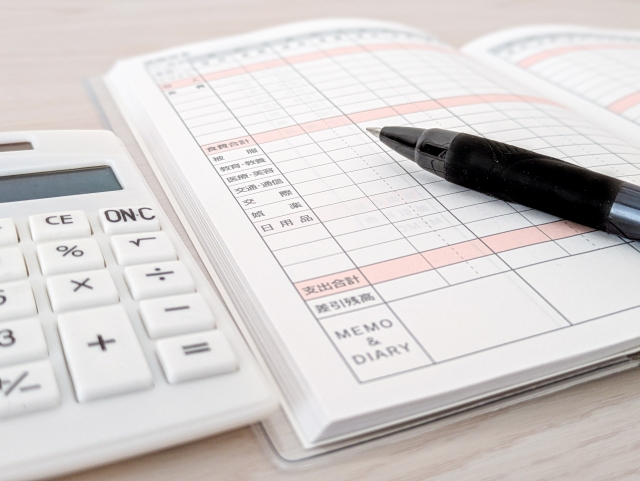
スマホを選ぶときによく相談者に言われる言葉で、「そんなにいいもの買っても、使いこなせないよ」なんて言葉があります。確かにスイスアーミーナイフのつまようじだけ使っていたらもったいない。
NASに関しても、ただのデータ置き場として使うだけなら赤字です。電源を入れておくだけでも、標準的な2ベイモデルのNASであれば、最大15W程度の消費電力です。電気代だけで一か月で300円程度かかる計算です。高性能だったり、4ベイ以上のモデルならさらに上を行きます。今話題のUGREENのNASyncシリーズでは、基本的にすべて高性能ですので、このあたりの電気代をきっちり計算に入れておいたほうがいいでしょう。
電気代で300円程度だと、100GB程度のクラウドストレージの月額と大して変わりません。そのうえ管理だの、バックアップだの、作業で自分自身の人件費(時間コスト)も使われることになります。
クラウドとの比較
利点も多いが手間も多いのがNASということを説明しました。これまでの話も含めてクラウドストレージと比較してみました。ユーザーが多いと思われるiCloudとGoogleドライブを対象にしています。大容量が当たり前のNASを比較対象とするため2TBのプランとしています。
| 項目 | iCloud | Googleドライブ | NAS (ネットワーク接続ストレージ) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | なし(無料プランあり、有料プランは月額課金) | なし(無料プランあり、有料プランは月額課金) | 高い(本体+HDD/SSDの購入が必要)概ね3万円スタート |
| ランニングコスト | 月額課金(2TBプランで約1,500円/月) | 月額課金(2TBプランで約1,450円/月) | 電気代+メンテナンス費用(月間300円前後+年間数千円~1万円以上) |
| データの保存場所 | Appleのデータセンター | Googleのデータセンター | 自宅やオフィス内のNAS本体 |
| アクセス性 | インターネット接続があればどこからでもアクセス可能 | インターネット接続があればどこからでもアクセス可能 | 基本的にローカルネットワーク内、外部アクセスには設定が必要 |
| アクセススピード | 回線スピードに依存 | 回線スピードに依存 | 自宅内では高速・外出時は回線スピードに依存 |
| バックアップ | 自動バックアップ機能が標準搭載 | 自動バックアップ機能が標準搭載 | 機器の購入が必要。手動または設定が必要 |
| セキュリティ | Appleによる管理(暗号化、二重認証など) | Googleによる管理(暗号化、二重認証など) | 自己管理(設定次第でセキュリティ強化可能) |
| 容量の拡張性 | プラン変更で簡単に拡張可能 | プラン変更で簡単に拡張可能 | HDD/SSDを追加購入して拡張 |
| 管理の手間 | ほぼ不要(自動化されている) | ほぼ不要(自動化されている) | 高い(設定やメンテナンスが必要) |
| 多機能性 | 主にデータ保存と同期 | 主にデータ保存と同期 | ストリーミング、仮想化、バックアップなど多機能 |
| 初期設定 | アカウント作成・ログインのみで即利用可能 | アカウント作成・ログインのみで即利用可能 | ネットワーク設定、RAID構成設定、アクセス権限の設定が必要 |
| 必要な知識 | 必要なし(初心者でも問題なく利用可能) | 必要なし(初心者でも問題なく利用可能) | 基本的なネットワーク知識やストレージ管理の理解が必要 |
| 適したユーザー | 手軽さを求める初心者やApple製品ユーザー | 手軽さを求める初心者やGoogleユーザー | ITリテラシーが高い(高くなりたい)、管理を楽しめるユーザーと設置場所を確保できるユーザーそして苦労するのが好きなユーザー |
この表からわかることは、決してクラウドストレージが法外な値段ではないという事実です。高度な自動化、スマホ買い替えによるデータ移行などまでも、すべて自動になる。このメリットを無視してNASに移行するのは非常に危険だと思います。
で、ここからが本当にNASの恐い話です。
NASではHDD故障の後、HDDを交換するという手間が発生しますが、ここの精神的な負荷が非常に大きい。HDDが1台故障して、その交換品を発注し、届いて、載せ替えて、RAIDのリビルドが無事に完了するまで安心できません。おまけに初心者はこのHDDの選び方でたぶん迷うことになります。この間スムーズにいって、約3~4日です。その間にもう1台故障しても、リビルド失敗でも、大量のデータが損失します。そしてこの可能性はNASユーザー全てが平等に抱えています。HDDとはそういうものです。バックアップがあればとりあえず安心ともいえますが、それすらなかったらお金に換えても、思い出は戻ってきません。さらに、これは故障にすぐ気づいた場合の話です。
・思い出はお金で買い戻せない。NASにバックアップは絶対に必須!(まだここでもお金がかかる)
・故障対応はRAIDリビルドが終わるまでが作業。この間3日ほど不安に駆られる!
・これ以上は書くのが嫌になるほどリビルドの結果待ちは怖い!
万人にはお勧めできない理由
もう十分上に書きました。NASを起点としたいろいろなことに向き合う覚悟、それに応じて自分のITリテラシーを鍛え上げる覚悟、それでも自分でデバイスとデータを掌握して、管理することで悦に浸れる特殊な人に向けた機械ということがわかると思います。いや、わかってくれ。
あと、クラウドストレージの2TBでも足りない人にも向いているかもしれない。このあたりのユーザーは必然的にリテラシーが高いと思われるので、こんな記事読まなくてもご自身で損益分岐点を割り出すことができるのではないかと思います。
ただ、個人的な願いを言わせてもらうのであれば、安易な広告につられて、インフルエンサーに踊らされて、ライトユーザーが手を出してしまい、その後埃をかぶって通電だけしている黒い箱になるのだけは見たくない。
ここで補足になりますが、Office365には1TBのOneDriveというクラウドストレージが付属しています。これもスマホアプリ、PC or Macアプリ、どちらもリリースされています。料金は2025年3月現在、月額換算1,775円です。2TBまではいらないけど、Officeは必要という方にはこちらのほうが刺さるのではないかと思います。セールを狙って購入するとさらにコスト圧縮可能です。しかもOneDriveは汎用ストレージなので、写真・動画以外にもなんでも放り込めます。
| マイクロソフト Microsoft 365 Personal 価格:21,300円(税込、送料無料) (2025/3/16時点) 楽天で購入 |
家族で使う場合はFamilyもあります。料金は2025年3月現在、月額換算2,283円です。ですが、1TBが6人分=合計6TB。一人分の月額は380円になってしまいます。もはやクラウドストレージタダ。
結論:万人にはお勧めできない
最後に怖い話を書いてしまいましたが、私はそれでもNASユーザーであり、きっとこれからも変わらないと思います。いろいろな課題があり、トラブルがあり、それらを楽しみながら乗り越えていけるユーザーには超絶おすすめです。トラブルは無い方がいいですが、HDDは消耗品なので仕方ないとしても、基本的に私が使ったことのあるSynology DS423+や、DS418jに関しては、本体の故障は一度もありませんでした。
特にHDDが日常的に余っていたり、自作PCを楽しむような逸般の誤家庭の方には、ハードルも低く、機器調達に困ることはないと思います。
NASユーザーになることで、得られる経験・スキルなどはコストに代えがたいものです。IT機器が無い企業もほぼありませんので、場合によっては仕事で役に立つこともあるでしょう。数字に表れないコストと、数字に表れない経験をうまく計算できる方は、ぜひ導入して快適なNASライフを送っていただければと思います。





コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい NASのヘビーユーザーだからこそ語れる。クラウドストレージの良さ UGEEN NASyncの広告を触発を受けてシリーズの第何段か忘れましたが、続編です。クラウドストレ […]