私はこれまで多くのネットワークストレージを使ってきました。仕事での経験を含めると収拾がつかなくなるので、今回は個人用および家庭用として利用したネットワークストレージについて焦点を当てて、ネットワークストレージ遍歴を紹介していきたいと思います。そのうえで、Synology DS423+は今の私にとって最適解であり、様々なモデルや運用をしてきたからこそ、今後もこのモデルを使い続けるであろうと確信しています。
ファイルサーバー沼(NAS沼)に最初に嵌ったとき
この深くて深くて抜け出しようのない沼の最初の入り口は、Windows Home Server 2011(WHS2011)までさかのぼります。
自作PCをたしなんでいる方(自作er)ならばご存じだとは思いますが、2011年の夏、6,980円で投げ売りが開始されました。当然自作PC界隈のネット民の間で、「WHS2011安いぞwwww」みたいな情報が出回り始めます。

当時は自作erを中心にしていたと思います。当然それを動かしてみたいと思ったことでしょう。私もその一人でした。サーバーOSであることから、一般的な利用を目的としたPCとは要件がちょっと違っていることも、自作erたちの興味を引いていたと思います。
手段(PC自作)を目的とした者たちに、目的(作る理由)を与えるとこうなるといういい例ですね。
単に安かったからという理由と、PCを作る目的を与えられたことによりこの沼に溺れることになりました。
Windows Home Server2011時代
初めて触るサーバーOSでした。2025年現在、家庭用に売られているNASはほぼこのころのWHS2011の機能と同等どころかそれ以上と呼べるだけ多機能になっていますが、当時のNASは本当にデータ置き場でしかなく、それ以上のことをさせようと思うとサーバーを構築するしかなかったと思います。
余っていたHDDを多数つなげて、Drive Extenderで巨大なドライブを作ったり、差分バックアップ機能(ボリュームシャドウコピー)、外出先からのアクセス、自宅内での映像ストリーミングなど、現在のNASでは当たり前の機能が実装されていました。

自宅内にあるPCのデータが、このころからすべてWHS2011に集中して入れられるようになり、PCはそのデータを使う端末としての運用スタイルが確立されていきました。そしてその「WHS2011祭り」は2016年のサポート期限とともに、後継製品打ち切りとともに終わっていったのです。
当時はWHS2011ユーザーの難民が多数存在し、後継製品はどうするかみたいな情報交換も活発に行われていたことを覚えています。
Windows 8 Pro時代
ちょうどその頃は、Windows 8のリリース後評価が安定してきた頃でした。
Windows 8自体はクライアントOSですが、ProエディションにはWindows Serverで培われたストレージ管理機能が進化して搭載されることとなり、その名も記憶域プールという名前でした。この機能は、ストレージを複数まとめてプールして、そこから仮想的なストレージを自分の必要な分だけ切り出していくという当時の仮想化技術の最先端でした。この機能が、WHS2011のDrive Extenderを使っていたユーザーの受け皿にもなった格好です。
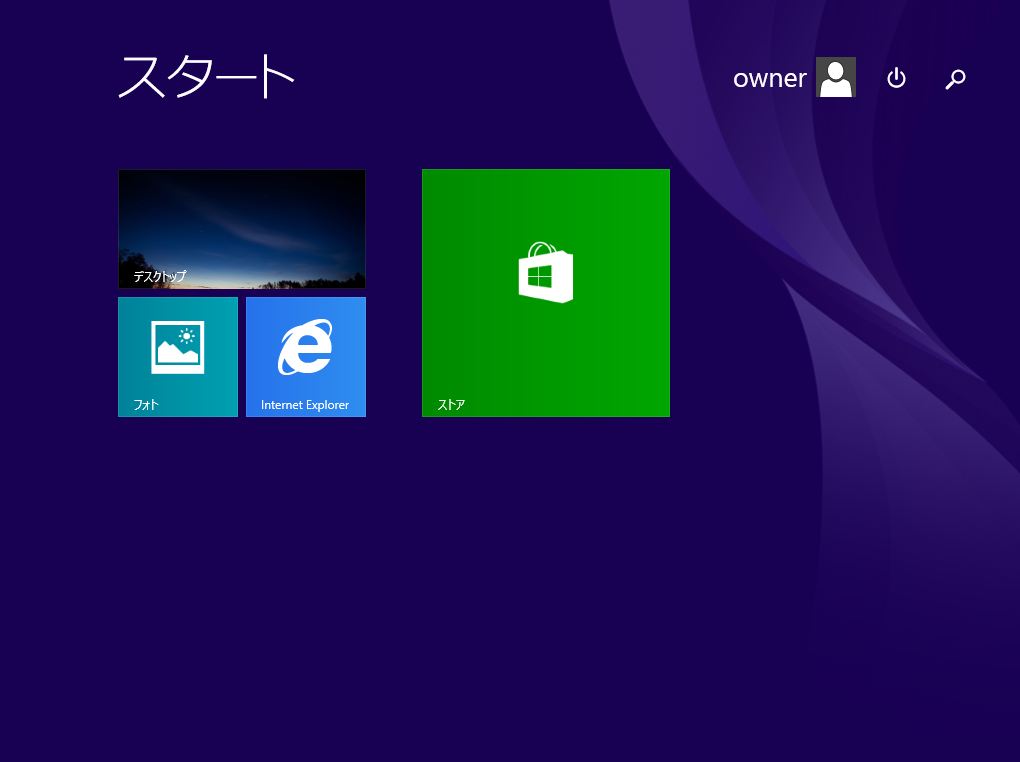
私自身は外出先からのアクセスや映像ストリーミングなどはもともとあまり使っていなかったこともあり、それらの機能をあきらめ、記憶域プールで巨大ストレージとしたデータ置き場としての「ファイルサーバー的運用」をWindows 8 Proで始めました。
ただ、この運用も長くは続けていませんでした。何よりアクセスが遅かったり、クライアントOSをサーバー的運用で使う場合、ライセンスの問題が浮上しかねないなという漠然とした不安です。接続ユーザーは2名しかいなかったので、問題はなかったとは思いますが、なんとなくもやもやしたまま使っていました。
Synology DS418j時代
初めてのNAS製品になります。Windowsの記憶域プールに似たSynology Hybrid RAIDの魅力に憑りつかれて、乗り換えることにしました。何よりWindows 8 Pro時代でできなかったストリーミングや、外出先からのアクセスがまたできるようになったことの恩恵は大きかったです。
構築はサーバーなどWindowsなどの汎用OSと比べて圧倒的に簡単で、マニュアルも充実しています。
仕事場などから自分のスマホでNASの中のデータを見たり、必要なデータを取り寄せて閲覧したりなど、自分の脳の外部記憶装置としても機能していました。
一番重宝したのは、当時使っていた音楽プレーヤーのウォークマンに、今すぐ聞きたい曲を入れるためにスマホからNASにアクセスして、そのスマホからウォークマンにBluetoothで転送(今思えばめんどくさw)して使っていました。まだストリーミングが一般的ではなかったこともあり、スマホを音楽プレーヤーとして使うことに抵抗もあり、この運用が気に入っていました。

アクセススピードも速く、ほぼ不満のない状態でしたが、ある日Amazon Prime PhotoとNASの連携機能がAmazon側の仕様変更によりできなくなったため、後釜を考え始めるようになりました。Amazon Prime Photoは写真を無制限でアップロードできるフォトストレージで、バックアップ的な側面もあり利用していたため、バックアップ先がないことが一つの不安要素になってしまいました。また、屋外IPカメラが3台に増え、SynologyのNASでは標準ライセンスでは2台までの録画となり、1台分の録画ができなくなることから、またWindows Serverに乗り換える気持ちがふつふつとわいてきました。(のちにライセンス購入で3台以上の録画ができることを知る…)
Windows Server 2022
リリースされたばかりのWindows Server 2022を仕事柄格安で入手できることとなり、検証もかねて自宅に導入することにしました。サーバーのハードウェアは当時余っていたジャンクの寄せ集めでしたが、せっかくWindowsに戻るならエンコードもやろうと考えつくわけです。HDDの搭載数も合計7台に上り、「より多くのHDDを搭載できるPC」を目指して構築しました。
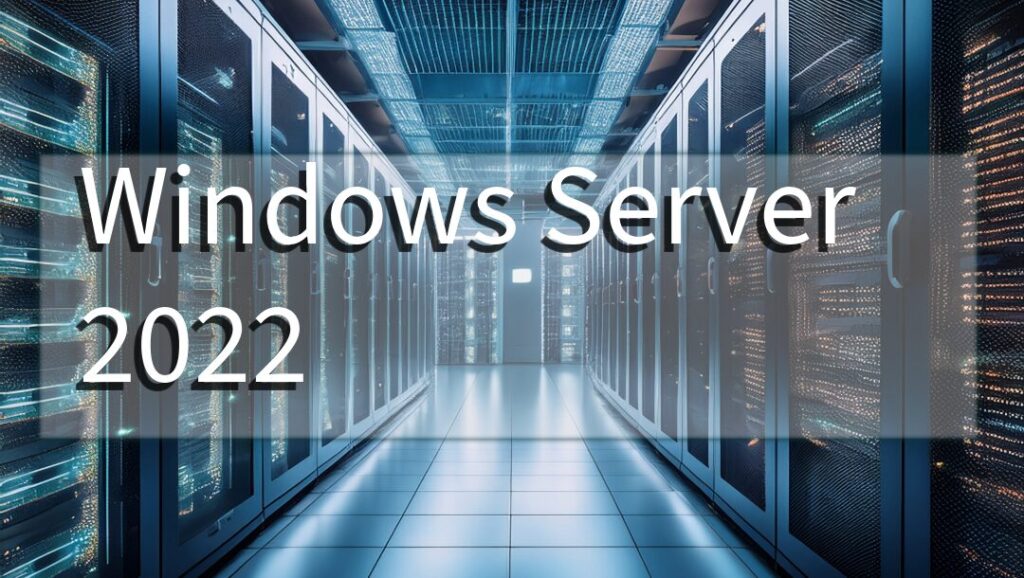
屋外IPカメラについても、iSpyというオープンソースのソフトウェアを使って3台とも録画できるようになりました。Amazon Prime PhotoについてもWindowsOSなので問題なくアプリが動作してバックアップ環境が整いました。しかし問題はストレージの設計・構築が複雑すぎたことです。アクセススピードもSSDをキャッシュに使っていたにもかかわらず、非常に遅かったため、不満がたまっていきました。
Synology DS423+
人間は、一度上げたスペックを落としたくないもの。そのためストレージ性能だけはSSDキャッシュが搭載できるものから選びました。Amazon Prime Photoに関しては、別のWindowsPCからバックアップをすることにして、屋外IPカメラはスタンドアロンでの録画をすることにしました。
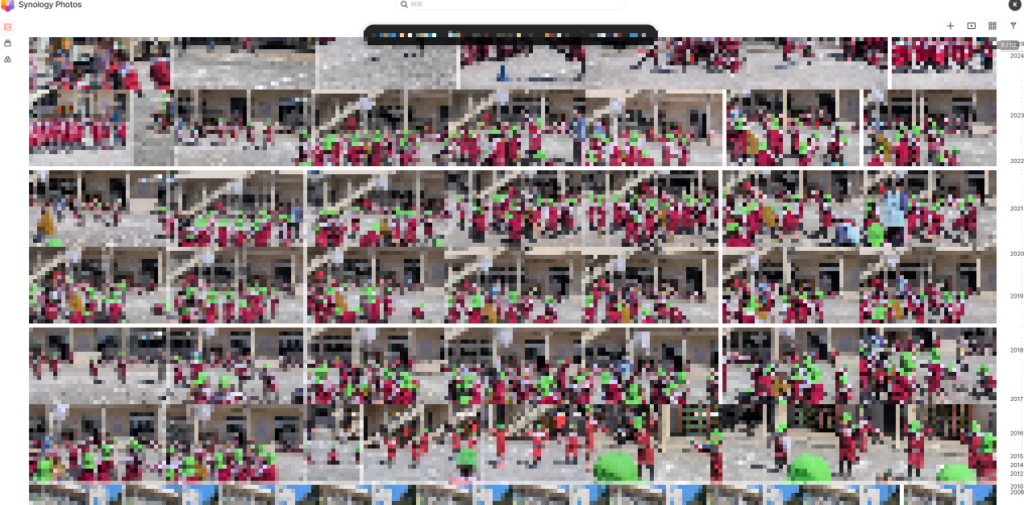
携帯からの写真アップロードは、Synology Photosというアプリで動画・静止画ともに自動でNASにアップロードできるという点も非常に心強く、Google Photoのバックアップを一切使わなくなりました。NASにため込んだ音楽データを外出先でストリーミングできるようになったことも非常に重宝しています。
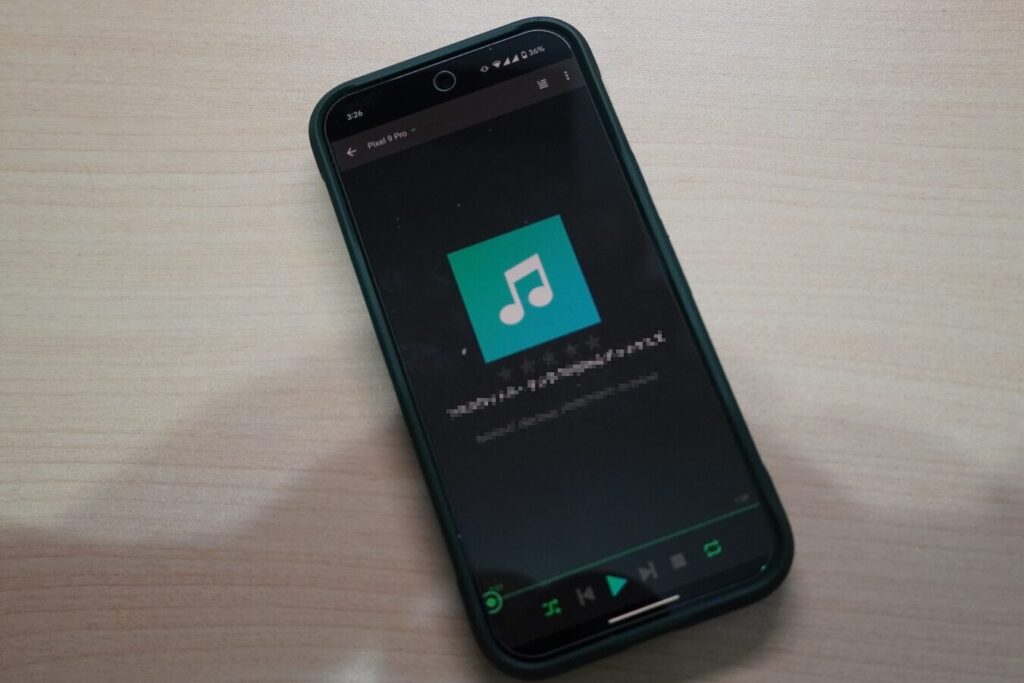
TP-LinkのIPカメラは、スマホアプリから複数台見ることが簡単かつ快適だったことも要因の一つです。こうなってくるとWindowsサーバーである理由はほぼなくなり、エンコードは時々実行すればいいのでメインマシンでエンコードすることにしました。
変遷の中で得られた教訓:シンプルであるべし
複雑怪奇なシステムは構築したり、問題を解決したりする過程は非常に楽しく、そして乗り越えた時の達成感は格別なものです。ですが、家庭内システム運用となると、管理者は私だけ、問題が起きなければほったらかしになります。そして実際に問題が起きた時は、構築時の記憶がほぼない。メンテナンスがすぐできない。となると、また厄介な問題となりました。
企業であれば、チームで動くことが主体ですので、ドキュメントに残したり(家庭でも残せばいいんでしょうが)チーム内の情報として各メンバーに蓄積されていきます。限られた予算の中で保護されたデータもまた、損失が恐いため、思い切ったことができないことも足かせとなっていました。
そういった問題に立ち向かうときにしたって、システム自体がシンプルである方が後からのメンテナンスが容易になります。その重要性をSynologyはわかっていて、このような製品をリリースし続けているんだろうなということが学べました。
今となっては、HDDの容量は4ドライブが同一の容量となったこともあり、Synology Hybrid RAIDである必要もなくなりました。またRAIDの恐ろしさも、この変遷の中で学んだこともあり、設計を見直すことでRAIDをやめようとも考えています。

ですが、生活スタイルが変わったり、勤務先が変わっても、何かしらの機能で恩恵をもたらしてくれるSynologyのアプリの豊富さは非常にありがたいです。そのたびに小さな発見もあったりと、使っていて飽きないNASという意味でも非常に優れた製品なんじゃないかなと思います。
基本機能であることはしっかりしていて安定しているにもかかわらず、安定を求めるユーザー、冒険心あふれたユーザー、飽き性なユーザー、HDDにそんなにお金をかけられないユーザーに対しても、訴求できる懐の深さが、まさにSynologyの魅力なんだと思いました。


コメント